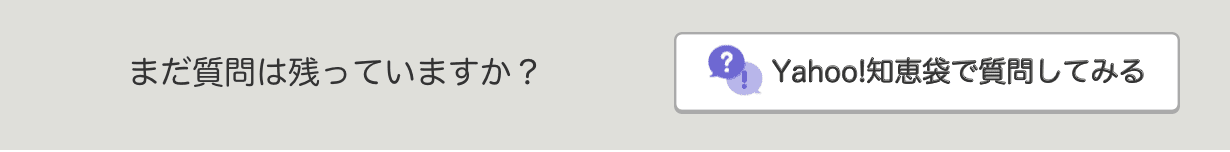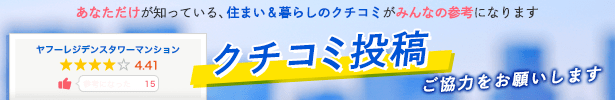教えて!住まいの先生
Q 家の配線を見ると、照明器具の(片切り)スイッチに、配線されているのが、N側 L側 とバラバラに配線されています。本来正しい配線が有ると思うのですが、 N(白)が、スイッチ?それとも器具側ですか?
①N(白)------スイッチ‐‐‐‐‐‐負荷-----L(黒)
②L(黒)------スイッチ‐‐‐‐‐‐負荷-----N(白)
どちらが基本?
お二方の説明を読むと、逆の事を言っているようで、どちらだか解らなくなってしまいました・・・・。
安全面から言うとどちらなのでしょうか?
質問日時:
2007/10/20 11:24:27
解決済み
解決日時:
2007/10/20 17:46:39
回答数: 2 | 閲覧数: 29606 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 2 | 閲覧数: 29606 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2007/10/20 17:46:39
住宅のスイッチで壁などに設置されているスイッチの事ですか、器具に内蔵されているスイッチですか?
どちらとも取れる文面ですが、取り合えず壁などに設置されているスイッチからお話します。
基本的に住宅、マンション、工場、その他、どの様な建物でも一緒ですが、黒(電源側、L)、白(接地側、N)が約束事なのですが
スイッチ結線の場合は少し事情が違います。
①電源(ブレーカー)→②黒線→③スイッチ→④白線→⑤負荷(照明など)→⑥電源の接地側へ帰る
これがスイッチの一般的な配線ですが、スイッチが2個、3個とある場合は少し事情が違います。
壁に下ろす配線が3本でスイッチ2個、この場合赤白黒と3本下ろします
スイッチ3個の場合黒白×2条下ろすので、黒白黒白と4本下ります。
この場合白2本が一般論に該当しますが、残りもう一本の黒線が帰り線となります。本来白線で帰す(器具へ送る)事が出来
れば良いのですが、ケーブルの種類でそれが出来ません。
これが白黒混在してしまう原因です、現在のケーブル配線方法ではどうし様も無い事です。
これを直す事(統一性を持たせる)も出来ますがコスト的に3倍位掛ってしまうでしょう。(配管を用いてIV配線)
スイッチ部分の見分け方は黒線(電源)と他のスイッチとの渡り線があるのが電源側で単独で出ている配線が負荷側です。
負荷側といっても接地側ではありません、器具へ送る電源側となります。
器具本体には2本線が行きますがそこには電源側と、接地側の両方がある事になります。
途中でジョイントをしているので器具には黒白と両方行っているはずです。下記の様な色の組み合わせ。
①電源(ブレーカー)→②黒線→③スイッチ→④白線(ジョイント)黒線→⑤負荷(照明など)→白線→⑥電源の接地側へ帰る
原則的にスイッチの入れる場所は電源と負荷の間に入れるのが常識です。
そうすればスイッチでオフにすれば器具には電源(100V)が行っていないので感電する事がありません。
接地側がそのまま繋がってますが、接地側は対地電圧が0Vですので触っても感電する事はありません。
分かりずらいと思いますが、スイッチ結線の場合途中でジョイントを行い、違う色(黒と白)をジョイントして色合わせを行いますので
スイッチ部分の色は素人さんでは少し分からないと思います。
器具に行っている線は黒(電源)、白(接地側)が基本です。
器具内部の色分けもこの様になっているのが基本です。
【補足に対する回答】
②L(黒)------スイッチ‐‐‐‐‐‐負荷-----N(白)になります。
他の方が言っている事、「口金のシェル側(外側)がN」も正解ですね。
只、最後の方でスイッチは接地側に付けると言う説明がありますが、これですとスイッチを切っても負荷に電圧が掛ってしまい
例えば電球交換などの場合口金の電源側に100Vが出ていますので危険です。
電源----負荷(器具)---スイッチ---N の場合は危険です。
安全なのは上記②の位置関係です。
前にも書きましたがスイッチを切る事によって器具には電圧が一切掛らないと言う事、感電する危険が無いと言う事です。
N側は対地0ボルトですので触れても大丈夫と言う事です。
もしテスター等があればコンセントの電圧を測ってみてください。(地面との対地電圧)
コンセントの形状で縦に2本の差込がありますが、向かって左側と言うのはN側(対地0ボルト)、右が対地100Vになっています。
測定の仕方はテスターの1本を左側へ、右を地面に(金属の棒を地面に挿し電線で延長する)→結果0ボルト
同じく右側と地面で結果100Vとなります。
もし近くに(エアコンなど)アース付きのコンセントがあればそのアースが地面の代用できます。
※建築設備(電気と設備)に従事している者です。
どちらとも取れる文面ですが、取り合えず壁などに設置されているスイッチからお話します。
基本的に住宅、マンション、工場、その他、どの様な建物でも一緒ですが、黒(電源側、L)、白(接地側、N)が約束事なのですが
スイッチ結線の場合は少し事情が違います。
①電源(ブレーカー)→②黒線→③スイッチ→④白線→⑤負荷(照明など)→⑥電源の接地側へ帰る
これがスイッチの一般的な配線ですが、スイッチが2個、3個とある場合は少し事情が違います。
壁に下ろす配線が3本でスイッチ2個、この場合赤白黒と3本下ろします
スイッチ3個の場合黒白×2条下ろすので、黒白黒白と4本下ります。
この場合白2本が一般論に該当しますが、残りもう一本の黒線が帰り線となります。本来白線で帰す(器具へ送る)事が出来
れば良いのですが、ケーブルの種類でそれが出来ません。
これが白黒混在してしまう原因です、現在のケーブル配線方法ではどうし様も無い事です。
これを直す事(統一性を持たせる)も出来ますがコスト的に3倍位掛ってしまうでしょう。(配管を用いてIV配線)
スイッチ部分の見分け方は黒線(電源)と他のスイッチとの渡り線があるのが電源側で単独で出ている配線が負荷側です。
負荷側といっても接地側ではありません、器具へ送る電源側となります。
器具本体には2本線が行きますがそこには電源側と、接地側の両方がある事になります。
途中でジョイントをしているので器具には黒白と両方行っているはずです。下記の様な色の組み合わせ。
①電源(ブレーカー)→②黒線→③スイッチ→④白線(ジョイント)黒線→⑤負荷(照明など)→白線→⑥電源の接地側へ帰る
原則的にスイッチの入れる場所は電源と負荷の間に入れるのが常識です。
そうすればスイッチでオフにすれば器具には電源(100V)が行っていないので感電する事がありません。
接地側がそのまま繋がってますが、接地側は対地電圧が0Vですので触っても感電する事はありません。
分かりずらいと思いますが、スイッチ結線の場合途中でジョイントを行い、違う色(黒と白)をジョイントして色合わせを行いますので
スイッチ部分の色は素人さんでは少し分からないと思います。
器具に行っている線は黒(電源)、白(接地側)が基本です。
器具内部の色分けもこの様になっているのが基本です。
【補足に対する回答】
②L(黒)------スイッチ‐‐‐‐‐‐負荷-----N(白)になります。
他の方が言っている事、「口金のシェル側(外側)がN」も正解ですね。
只、最後の方でスイッチは接地側に付けると言う説明がありますが、これですとスイッチを切っても負荷に電圧が掛ってしまい
例えば電球交換などの場合口金の電源側に100Vが出ていますので危険です。
電源----負荷(器具)---スイッチ---N の場合は危険です。
安全なのは上記②の位置関係です。
前にも書きましたがスイッチを切る事によって器具には電圧が一切掛らないと言う事、感電する危険が無いと言う事です。
N側は対地0ボルトですので触れても大丈夫と言う事です。
もしテスター等があればコンセントの電圧を測ってみてください。(地面との対地電圧)
コンセントの形状で縦に2本の差込がありますが、向かって左側と言うのはN側(対地0ボルト)、右が対地100Vになっています。
測定の仕方はテスターの1本を左側へ、右を地面に(金属の棒を地面に挿し電線で延長する)→結果0ボルト
同じく右側と地面で結果100Vとなります。
もし近くに(エアコンなど)アース付きのコンセントがあればそのアースが地面の代用できます。
※建築設備(電気と設備)に従事している者です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2007/10/20 17:46:39
本来資格が無いといじれないのでしょうが、資格のある方が、配線してバラバラでは、自分でやったほうが、安心出来ます。確認すると、浴室の照明が、L線にスイッチがN線に繋がっています。その他、全く統一性が無く取りやすいほうから取っていると言う感じです。機会があれば、配線し直して置きたいです。
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2007/10/20 12:12:07
照明器具の場合、基本は以下のようになっています。理由は万一の場合の感電リスクの軽減と漏電リスクの軽減。
白熱電球、ハロゲン電球、チョークレス水銀灯の場合、口金のシェルにつながっている側が接地側(単層3線の場合N)。
蛍光灯、HIDの場合、安定器がつながっている側が接地側(単層3線の場合N)。
電子安定器、または電子安定器が内蔵されたコンパクト蛍光灯、電球型蛍光灯の場合、口金の外側(またはシェル側)につながっている方を接地側(単層3線の場合N)。
照明器具に限らず電気器具一般論では、片切りスイッチはすべて接地側に付けるのが私の好みです(この方が安全)。
1時間ほど前に回答したのにミスがありましたので、修正しました。
白熱電球、ハロゲン電球、チョークレス水銀灯の場合、口金のシェルにつながっている側が接地側(単層3線の場合N)。
蛍光灯、HIDの場合、安定器がつながっている側が接地側(単層3線の場合N)。
電子安定器、または電子安定器が内蔵されたコンパクト蛍光灯、電球型蛍光灯の場合、口金の外側(またはシェル側)につながっている方を接地側(単層3線の場合N)。
照明器具に限らず電気器具一般論では、片切りスイッチはすべて接地側に付けるのが私の好みです(この方が安全)。
1時間ほど前に回答したのにミスがありましたので、修正しました。
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション

3LDK以上のマンション
-
賃貸物件

ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション

駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て

南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て

リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地

南側に道路がある土地