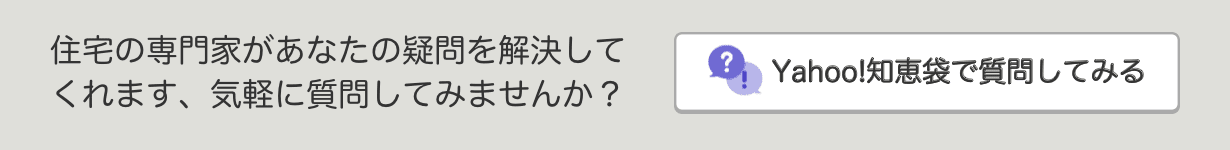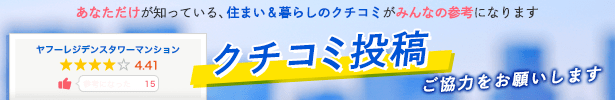教えて!住まいの先生
Q 中世ヨ-ロッパの三圃制と日本の二毛作はどういう点で決定的な違いがあるのですか? また同じ時期でありながら,どうしてそのような違いが生じたのですか?
(できれば経済的な側面からお答え下さい。)
質問日時:
2010/4/23 12:16:42
解決済み
解決日時:
2010/4/24 10:14:14
回答数: 1 | 閲覧数: 1726 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 1 | 閲覧数: 1726 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2010/4/24 10:14:14
三圃制の目的は連作障害の回避です。それに対し、二毛作は収穫量向上が目的です。ヨーロッパでは麦作がメインだったから、三年サイクルで土地を使いまわして連作障害を回避する必要があった。それに対し日本は稲作がメインです。稲の生育時期は水田として土地を使うので、それが連作障害回避に効果があったのです。水稲というのは連作障害回避をしながら、土地を有効活用するという知恵でした。稲というのは地上最強の農作物なのだ。だから山地ばかりで、可住面積が少ない日本でも、これだけの人口を抱えることができる。しかし稲は本来亜熱帯~温帯の植物なので、寒冷地では育ちません。だから亜寒帯のヨーロッパでは稲を作りたくても作れない。だから仕方なくヨーロッパでは小麦が中心になった。小麦だけでは食べていけないから牧畜も盛んだ。ヨーロッパは平地が多いのに人口は多くない。例えば日本とドイツは国土面積はほとんど同じです。しかし可住面積は日本はドイツの半分程度しかないのだ。大まかにいえば日本は1/3程度でドイツは2/3ぐらい。ヨーロッパ諸国はどこも2/3以上は可住面積です。しかし、それでも日本はドイツの1.5倍もの人口があるのです。これが稲が地上最強の農作物だという意味です。ちなみに米には小麦に含まれない必須アミノ酸も多く、大豆食品と組み合わせることで必要な必須アミノ酸が補給できてしまうのに対し、小麦は大豆食品と組み合わせても足りない。だから欧米人は肉を食べて、足りない必須アミノ酸を補う必要がある。こういうことをどうして学校では教えないのかなあ。
【追加】
念のため、付け加えれば小麦は水稲とは逆で排水性が重要になります。だから乾燥した土地でも栽培できる。水稲は灌漑設備が必要です。二毛作は、表作で稲をつくり、裏作で小麦・菜種等を栽培します。それは冬季はさすがに稲作に必要な気温が得られない地域が多いからです。九州・四国の温暖な地域では冬季でも稲作が可能で、一時期、二期作も行われていました。現代では、米の需要が減少して減反政策を実施しているぐらいですから、二期作は行われいません。いずれにせよ、二毛作も二期作も連作障害の回避は目的ではありません。単純に収穫量増産が目的でした。
【追加】
念のため、付け加えれば小麦は水稲とは逆で排水性が重要になります。だから乾燥した土地でも栽培できる。水稲は灌漑設備が必要です。二毛作は、表作で稲をつくり、裏作で小麦・菜種等を栽培します。それは冬季はさすがに稲作に必要な気温が得られない地域が多いからです。九州・四国の温暖な地域では冬季でも稲作が可能で、一時期、二期作も行われていました。現代では、米の需要が減少して減反政策を実施しているぐらいですから、二期作は行われいません。いずれにせよ、二毛作も二期作も連作障害の回避は目的ではありません。単純に収穫量増産が目的でした。
質問した人からのコメント
回答日時: 2010/4/24 10:14:14
詳しく解説していただき,ありがとうございました。よく理解できました。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
土地

南側に道路がある土地
-
土地

前道6メートル以上の土地
-
土地

平坦地の土地