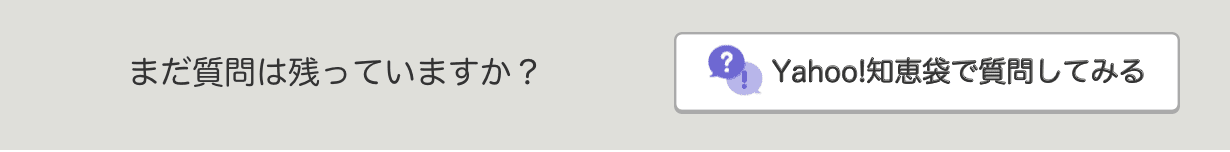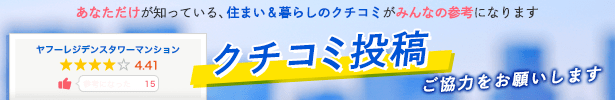教えて!住まいの先生
Q 江戸時代は民家や町家で2階建てはないのですか?
お金持ちでも1階建てのように思いますが。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2010/7/13 10:37:05
慶安のお触れ以降、民家や商家などの建物に対してその身分に応じての規制があり、新築等の場合には庄屋や町方肝煎を通じて代官所等に届け出が必要とされました。今日の建築確認の前身でありますが、この際審査され不必要な二階建ては却下されます。
しかし、地域風土によって建て方は異なるので、二階(またはそれ以上=合掌作りなど)が普通にある地域では認められています。例として輪中地帯の水害常襲地や豪雪地帯など、出入りの必要性が認められる場合。旅籠や料亭、妓楼など狭い土地活用が必要な所などでは、慣例として認められていますが、二階から表通りを見下ろすような作りは禁じられていて、通りに接した壁面の窓は違い格子など明かり取り程度とされ、また外観上二階に見えないようなデザインになっています。
いわゆる屋根裏部屋的な二階や中二階は、商家では倉庫に、農家では養蚕小屋として広く普及しています。
***
【蛇足】「下にぃ、下にぃ」という時代に二階建てが許されたことから「二階家」という屋号で呼ばれた旅館が佐渡の方にあります。それだけ特異な例でありました。
しかし、地域風土によって建て方は異なるので、二階(またはそれ以上=合掌作りなど)が普通にある地域では認められています。例として輪中地帯の水害常襲地や豪雪地帯など、出入りの必要性が認められる場合。旅籠や料亭、妓楼など狭い土地活用が必要な所などでは、慣例として認められていますが、二階から表通りを見下ろすような作りは禁じられていて、通りに接した壁面の窓は違い格子など明かり取り程度とされ、また外観上二階に見えないようなデザインになっています。
いわゆる屋根裏部屋的な二階や中二階は、商家では倉庫に、農家では養蚕小屋として広く普及しています。
***
【蛇足】「下にぃ、下にぃ」という時代に二階建てが許されたことから「二階家」という屋号で呼ばれた旅館が佐渡の方にあります。それだけ特異な例でありました。
質問した人からのコメント
回答日時: 2010/7/13 10:37:05
有難うございました。
回答
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2010/7/6 22:03:15
江戸時代は身分制が有ったので、民家や町家で2階建ては許されませんでした。
お金持ちでも1階建てでした。
でもシコロ造りと云う民家とか、「かぶと造り」と云う商家の建物は、中二階建でした。
でも原則として禁止されていたので、殆どが二階の窓を壁で覆って、外から窓が見えないように遠慮した造りにしていた。
但し神社仏閣は公家でも武家でもないけど、例外の存在として楼門や五重塔も建てました。
お金持ちでも1階建てでした。
でもシコロ造りと云う民家とか、「かぶと造り」と云う商家の建物は、中二階建でした。
でも原則として禁止されていたので、殆どが二階の窓を壁で覆って、外から窓が見えないように遠慮した造りにしていた。
但し神社仏閣は公家でも武家でもないけど、例外の存在として楼門や五重塔も建てました。
A
回答日時:
2010/7/6 21:57:02
普通に二階建ての長屋とかありましたが
A
回答日時:
2010/7/6 20:55:29
大河ドラマ龍馬伝で出てきた龍馬の家には二階がありました。
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
土地

南側に道路がある土地
-
土地

前道6メートル以上の土地
-
土地

平坦地の土地