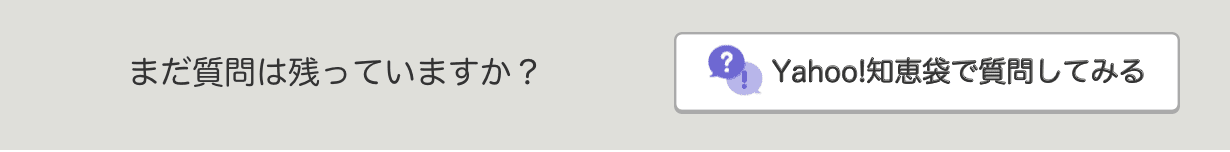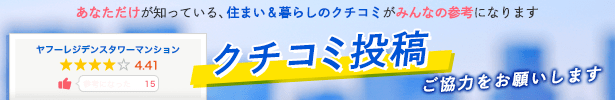教えて!住まいの先生
Q 住宅を建てる際の耐震等級について質問です。 現在悩んでいる工務店には、 許容応力度計算で耐震等級1〜3を選択できます。それにより金額差がある感じです。
また、制振ダンパーと耐力壁が標準となっています。
そこで下記質問です。
①制振ダンパーと耐力壁が標準となれば、許容応力度計算の耐震等級1や2でも強度的には問題が無いのか。また実際に等級1や2で建てた方は、後悔したことがあるのかお聞きしたいです。
②許容応力度計算の耐震等級1や2と、構造計算の耐震等級3ではどちらが地震に強い家なのでしょうか??
個人の価値観も含まれてくるのかなとは思いますが、いろいろな方の意見をお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。
そこで下記質問です。
①制振ダンパーと耐力壁が標準となれば、許容応力度計算の耐震等級1や2でも強度的には問題が無いのか。また実際に等級1や2で建てた方は、後悔したことがあるのかお聞きしたいです。
②許容応力度計算の耐震等級1や2と、構造計算の耐震等級3ではどちらが地震に強い家なのでしょうか??
個人の価値観も含まれてくるのかなとは思いますが、いろいろな方の意見をお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/11 22:49:59
品確法<構造計算(許容応力度計算)の関係にあるので、品確法の等級3は許容応力度計算の2くらいです
許容応力度計算の耐震等級3を取得した上で制振ダンパーをつけると、繰り返しの揺れにも安心かとおもいます。
耐震等級1は震度6強の揺れに対し一度だけ耐える(住めるという意味ではない)という意味合いがあり、変形などから隙間風や建具等に隙間やその他ヒビなどが入り、補修無しで住める事は保証されていません。また6強以上の揺れが複数回来ると倒壊する確率はあります。
ちなみに、木造(在来工法)の耐震等級3とRC造や鉄骨造の耐震等級1は同程度なので、木造では耐震等級3は必須だとおもいます。
木造でも、ツーバイフォーの耐震等級3>在来工法の耐震等級3という関係です。
許容応力度計算の耐震等級3を取得した上で制振ダンパーをつけると、繰り返しの揺れにも安心かとおもいます。
耐震等級1は震度6強の揺れに対し一度だけ耐える(住めるという意味ではない)という意味合いがあり、変形などから隙間風や建具等に隙間やその他ヒビなどが入り、補修無しで住める事は保証されていません。また6強以上の揺れが複数回来ると倒壊する確率はあります。
ちなみに、木造(在来工法)の耐震等級3とRC造や鉄骨造の耐震等級1は同程度なので、木造では耐震等級3は必須だとおもいます。
木造でも、ツーバイフォーの耐震等級3>在来工法の耐震等級3という関係です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/11 22:49:59
みなさま分かりやすいご回答をありがとうございます。
工法や材質によるそれぞれの地震強度や、耐震等級1に対する考えを簡潔におまとめいただいた方をベストアンサーにさせていただきました。
回答
8 件中、1~8件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2025/3/11 21:17:48
タフボードというのもある。
壁倍率4.5倍「タフボード」 柱間はめ込み式で耐力壁施工
2021年7月9日 15:06
https://www.s-housing.jp/archives/241027
壁倍率4.5倍「タフボード」 柱間はめ込み式で耐力壁施工
2021年7月9日 15:06
https://www.s-housing.jp/archives/241027
A
回答日時:
2025/3/9 23:01:50
等級1は、建築基準法で定められている最低基準と同じです。等級2は、その基準の1.25倍です。そして、等級3は1.5倍になります。等級1でも強度的に問題はありません。ただし、稀におこる大震災のようなものには耐えられないと思います。等級があがればあがるほど、倒壊の恐れは低くなるという感じです。
そして、許容応力度計算とは、計算プログラムに実際の建物情報を入力し、荷重・応力の伝達を自動計算し、1つ1つの部材について計算を行います。
壁量計算や、性能表示計算と言われるものは、プログラムではなく手計算で行えるような簡易的な計算です。
許容応力度計算の方が精密に数値がでるという感じです。壁量計算と呼ばれるものは、壁の量であったり、壁の配置、金物の検討、床材の検討などを行います。許容応力度計算はそれを精密に行い、更に、柱や梁の断面検討、基礎の検討などを行います。建物の設計により、荷重のかかり方は異なりますので、標準よりスパンが大きいですとか、部分的に荷重が大きくなるですとか、スキップフロアなどがある場合は許容応力度計算をした方が安全です。
自分は建てたことは無いので、後悔した点はお伝えできないのですが、個人的な意見としましては、壁量計算(性能表示計算)より、許容応力度計算をした時の方が、どこの耐力が不足していて、どのくらい偏心がおき、実際どの程度の寸法で足りるのかなどがはっきりと分かるので、許容応力度計算をおします。
許容応力度計算の等級1や2と、壁量計算の耐震3ではさすがに壁量計算の耐震3の方が地震には強いかもしれませんが、慎重に設計をしないと、思わぬとこが壊れる可能性があります。設計の建物がL字であるとか、細長いですとか、大きく吹き抜けてますとか、少しイレギュラーと思う時は許容応力度計算がいいかもしれません。
そして、許容応力度計算とは、計算プログラムに実際の建物情報を入力し、荷重・応力の伝達を自動計算し、1つ1つの部材について計算を行います。
壁量計算や、性能表示計算と言われるものは、プログラムではなく手計算で行えるような簡易的な計算です。
許容応力度計算の方が精密に数値がでるという感じです。壁量計算と呼ばれるものは、壁の量であったり、壁の配置、金物の検討、床材の検討などを行います。許容応力度計算はそれを精密に行い、更に、柱や梁の断面検討、基礎の検討などを行います。建物の設計により、荷重のかかり方は異なりますので、標準よりスパンが大きいですとか、部分的に荷重が大きくなるですとか、スキップフロアなどがある場合は許容応力度計算をした方が安全です。
自分は建てたことは無いので、後悔した点はお伝えできないのですが、個人的な意見としましては、壁量計算(性能表示計算)より、許容応力度計算をした時の方が、どこの耐力が不足していて、どのくらい偏心がおき、実際どの程度の寸法で足りるのかなどがはっきりと分かるので、許容応力度計算をおします。
許容応力度計算の等級1や2と、壁量計算の耐震3ではさすがに壁量計算の耐震3の方が地震には強いかもしれませんが、慎重に設計をしないと、思わぬとこが壊れる可能性があります。設計の建物がL字であるとか、細長いですとか、大きく吹き抜けてますとか、少しイレギュラーと思う時は許容応力度計算がいいかもしれません。
A
回答日時:
2025/3/9 16:31:39
構造計算と許容応力度計算は同じものです。構造計算で、評点3にして、ダンパーを付けるのが一番良いでしょう。私は設計事務所を入れた方がキチンと設計監理してくれるので安心だと思います。
A
回答日時:
2025/3/9 15:24:05
耐震補強についてこんな記事を見つけた。
参考にすべし。
↓
W耐震工法(筋交い+耐力壁)
ひのきの家に一段と耐震性・耐久性・気密性を高めるW耐震工法。
ひのき無垢柱に、耐震金物、筋交いに耐震壁をプラスし、
点と面で横揺れから家を支える地震に強い頑丈な工法です。
頑丈なだけでなく、断熱性・遮音性・省エネ性にも貢献しています。
市川建築事務所では、浜松でもいち早く耐力壁を取り入れ、
筋交いと耐力壁を併用して壁倍率5倍の 地震に強い
強固な構造の家を提供してきました。
住宅に併せて構造計算し、最適な配置・施工を行い、
耐震レベル3等級を高いレベルで実現しています。
https://ichikawakenchiku.co.jp/hinoki-no-ie/w-taishin/
「かべつよし」シリーズは、天井・床を壊さない
低コストな耐震補強工法として2000年に誕生しました。
面材や金物を改良し豊富なバリエーションをご用意しています。
一般的な壁補強に必要な天井・床の解体・復旧工事が不要なので、
低コストと工期の短縮を実現した耐震補強工法です。
https://www.aimkk.com/product/kabetuyosi.html
真上からかかる圧力に対しては柱も支える役割を果たしていますが、
水平方向からかかる圧力に対しては耐力壁が大きな役割を果たしています。
耐力壁にはいくつかの種類がありますが、木造住宅を建築する際の
軸組工法(在来工法)で、特に多く使われているのが筋交いを用いた
耐力壁です。
筋交いとは、柱・梁・土台で構成された四角形の枠内に斜めに
渡す補強材のことです。
この筋交いによって水平方向に対する強度が保たれ、
地震や台風時の建物の変形を防ぎます。
軸組工法(在来工法)では、一定の割合で筋交いを
入れなければいけませんが、枠組壁工法(ツーバイフォー工法)では、
耐力面材が耐力壁となっているため、筋交いは使用されていません。
なお、鉄筋コンクリート造でも耐力壁は必要で、壁内の鉄筋量と
壁の厚みによって耐力壁と非耐力壁を区別しています。
鉄筋コンクリート造の場合は「耐震壁」と呼ばれたりもします。
耐力壁はバランスよく配置することが重要です。
バランスが悪いと地震時の上下、水平方向の力やねじれに耐えきれず、
建物が倒壊する恐れがあります。
又、直下率を意識して上下階の耐力壁の位置をできるだけ
合わせるようにし、力の伝達をスムーズにします。
これは耐力壁だけでなく、柱にも同じことがいえます。
上下階の平面図を照らし合わせ、耐力壁と柱がなるべく
重ね合うように配置してあげた方が、建物の強度が強くなります。
耐力壁の配置だけでなく、筋交いの向き(方向)にも
注意が必要です。
筋交いが全て同じ方向を向いていると、片側の力には対抗できても、
もう片方の力には対抗力がなくなってしまいます。
筋交いの向きは交互に変え、ハの字もしくは逆ハの字に
しておく必要があります。
基本的には、1階がハの字で配置されている場合は
2階は逆ハの字に配置し、階層ごとに向きを変えていきます。
どのような向きで配置されているかを知りたいときは、
軸組図などで筋交いの向きを確認することができるので、
気になる方はチェックしておきましょう。
https://up-housing.jp/220222blog1/
第1回 【耐震・省エネ解説】耐震化、筋交い補強について。
熊本耐震改修研究所では、”熊本の家をより強くより美しく”を
コンセプトに、長く愛され続ける木造住宅を目指して、
住宅の耐震化と省エネ化を図っていきます。
このブログでは、耐震化改修・省エネ化改修についての
技術的内容や、分かりにくいところ、どんな方法があるのかな?
など、みなさまのハテナを少しでも解決できるよう、
解説していきたいと思います。
筋交い補強による耐震化改修
今回は、耐震化改修の中でももっとも普及している
「筋交い補強」についてです。
まずは、この筋交いについてその役割などを解説しますね。
筋交いとは、木造住宅における耐力壁を構成する構造体の一部です。
この筋交いは、建物に加わる横からの力(地震による力)に
抵抗して、建物の構造を安定させています。
絵にもあるように、引っ張られる力に威力を発揮しますので、
建物の右からの力、左からの力にバランスよく配置する必要があります。
実際にこの筋交いに力が加わるとどうなるか、
外からの力の方向(右とか左とか)によって、
その筋交いの取り付く柱に、土台から抜けようとする力や、
梁から抜けようとする力が発生します。
そんな柱の抜けに抵抗するのが「ホールダウン金物」と
呼ばれるものです。
また、筋交いと柱と土台や梁とをしっかり止め付ける金物を
「筋交い金物」といい、筋交いの接合部の補強を担う金物です。
これらがきちんと施工され、それぞれが持つ性能を発揮しないと、
安全な建物にはなることができません。
古い建物は、安全基準も古い。
古い建物(1981年以前の建物)では、現在の基準
(上の絵はほぼ現行基準)には至っておらず、
筋交いはあるものの金物での補強などは、ほとんど見られません。
当時の基準ではそれで良しとされていたので仕方ないですね。
これまで多くの地震が日本を襲い、その大地震ごとに
耐震基準が見直され、現代の基準へと変化してきました。
現在の基準ですら、法律を守っているだけでは、
危ういところがあるのも事実です。
構造安全性を高めようとすれば補強方法はいくつもありますが、
同時にコストもかかるため、どこまで補強するかの判断が
大切なところです。
https://kumamoto-taishin.com/info/%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%A7%E8%A7%A3%E8%AA%AC%EF%BC%81%E8%80%90%E9%9C%87%E6%94%B9%E4%BF%AE%E3%81%AE%E4%B8%AD%E8%BA%AB%EF%BC%88%E7%AD%8B%E4%BA%A4%E3%81%84%E8%A3%9C%E5%BC%B7%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88/
参考にすべし。
↓
W耐震工法(筋交い+耐力壁)
ひのきの家に一段と耐震性・耐久性・気密性を高めるW耐震工法。
ひのき無垢柱に、耐震金物、筋交いに耐震壁をプラスし、
点と面で横揺れから家を支える地震に強い頑丈な工法です。
頑丈なだけでなく、断熱性・遮音性・省エネ性にも貢献しています。
市川建築事務所では、浜松でもいち早く耐力壁を取り入れ、
筋交いと耐力壁を併用して壁倍率5倍の 地震に強い
強固な構造の家を提供してきました。
住宅に併せて構造計算し、最適な配置・施工を行い、
耐震レベル3等級を高いレベルで実現しています。
https://ichikawakenchiku.co.jp/hinoki-no-ie/w-taishin/
「かべつよし」シリーズは、天井・床を壊さない
低コストな耐震補強工法として2000年に誕生しました。
面材や金物を改良し豊富なバリエーションをご用意しています。
一般的な壁補強に必要な天井・床の解体・復旧工事が不要なので、
低コストと工期の短縮を実現した耐震補強工法です。
https://www.aimkk.com/product/kabetuyosi.html
真上からかかる圧力に対しては柱も支える役割を果たしていますが、
水平方向からかかる圧力に対しては耐力壁が大きな役割を果たしています。
耐力壁にはいくつかの種類がありますが、木造住宅を建築する際の
軸組工法(在来工法)で、特に多く使われているのが筋交いを用いた
耐力壁です。
筋交いとは、柱・梁・土台で構成された四角形の枠内に斜めに
渡す補強材のことです。
この筋交いによって水平方向に対する強度が保たれ、
地震や台風時の建物の変形を防ぎます。
軸組工法(在来工法)では、一定の割合で筋交いを
入れなければいけませんが、枠組壁工法(ツーバイフォー工法)では、
耐力面材が耐力壁となっているため、筋交いは使用されていません。
なお、鉄筋コンクリート造でも耐力壁は必要で、壁内の鉄筋量と
壁の厚みによって耐力壁と非耐力壁を区別しています。
鉄筋コンクリート造の場合は「耐震壁」と呼ばれたりもします。
耐力壁はバランスよく配置することが重要です。
バランスが悪いと地震時の上下、水平方向の力やねじれに耐えきれず、
建物が倒壊する恐れがあります。
又、直下率を意識して上下階の耐力壁の位置をできるだけ
合わせるようにし、力の伝達をスムーズにします。
これは耐力壁だけでなく、柱にも同じことがいえます。
上下階の平面図を照らし合わせ、耐力壁と柱がなるべく
重ね合うように配置してあげた方が、建物の強度が強くなります。
耐力壁の配置だけでなく、筋交いの向き(方向)にも
注意が必要です。
筋交いが全て同じ方向を向いていると、片側の力には対抗できても、
もう片方の力には対抗力がなくなってしまいます。
筋交いの向きは交互に変え、ハの字もしくは逆ハの字に
しておく必要があります。
基本的には、1階がハの字で配置されている場合は
2階は逆ハの字に配置し、階層ごとに向きを変えていきます。
どのような向きで配置されているかを知りたいときは、
軸組図などで筋交いの向きを確認することができるので、
気になる方はチェックしておきましょう。
https://up-housing.jp/220222blog1/
第1回 【耐震・省エネ解説】耐震化、筋交い補強について。
熊本耐震改修研究所では、”熊本の家をより強くより美しく”を
コンセプトに、長く愛され続ける木造住宅を目指して、
住宅の耐震化と省エネ化を図っていきます。
このブログでは、耐震化改修・省エネ化改修についての
技術的内容や、分かりにくいところ、どんな方法があるのかな?
など、みなさまのハテナを少しでも解決できるよう、
解説していきたいと思います。
筋交い補強による耐震化改修
今回は、耐震化改修の中でももっとも普及している
「筋交い補強」についてです。
まずは、この筋交いについてその役割などを解説しますね。
筋交いとは、木造住宅における耐力壁を構成する構造体の一部です。
この筋交いは、建物に加わる横からの力(地震による力)に
抵抗して、建物の構造を安定させています。
絵にもあるように、引っ張られる力に威力を発揮しますので、
建物の右からの力、左からの力にバランスよく配置する必要があります。
実際にこの筋交いに力が加わるとどうなるか、
外からの力の方向(右とか左とか)によって、
その筋交いの取り付く柱に、土台から抜けようとする力や、
梁から抜けようとする力が発生します。
そんな柱の抜けに抵抗するのが「ホールダウン金物」と
呼ばれるものです。
また、筋交いと柱と土台や梁とをしっかり止め付ける金物を
「筋交い金物」といい、筋交いの接合部の補強を担う金物です。
これらがきちんと施工され、それぞれが持つ性能を発揮しないと、
安全な建物にはなることができません。
古い建物は、安全基準も古い。
古い建物(1981年以前の建物)では、現在の基準
(上の絵はほぼ現行基準)には至っておらず、
筋交いはあるものの金物での補強などは、ほとんど見られません。
当時の基準ではそれで良しとされていたので仕方ないですね。
これまで多くの地震が日本を襲い、その大地震ごとに
耐震基準が見直され、現代の基準へと変化してきました。
現在の基準ですら、法律を守っているだけでは、
危ういところがあるのも事実です。
構造安全性を高めようとすれば補強方法はいくつもありますが、
同時にコストもかかるため、どこまで補強するかの判断が
大切なところです。
https://kumamoto-taishin.com/info/%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%A7%E8%A7%A3%E8%AA%AC%EF%BC%81%E8%80%90%E9%9C%87%E6%94%B9%E4%BF%AE%E3%81%AE%E4%B8%AD%E8%BA%AB%EF%BC%88%E7%AD%8B%E4%BA%A4%E3%81%84%E8%A3%9C%E5%BC%B7%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88/
A
回答日時:
2025/3/8 23:45:16
①今後、未曾有の大地震が来ることもあるかもしれません。耐震2+制振ダンパーで問題ないというコメントは誰も出来ないと思います。
②「許容応力度計算」や「保有水平耐力計算」などを構造計算と呼びます。
おそらく簡易計算方法である性能表示計算のコトを言われているのだと思いますが、簡易計算であるが故に構造計算と比べて結果には振れ幅が生まれると思われ、一概にどっちの方が強いと断定はできない(ケースバイケース)と思います。
構造計算の方が結果の信頼性が高いと言えることは確かです。
私も現在建築中ですが、今後予想外の地震が来るかも知れないという事も踏まえ、許容応力度の耐震3+制振にしています。
②「許容応力度計算」や「保有水平耐力計算」などを構造計算と呼びます。
おそらく簡易計算方法である性能表示計算のコトを言われているのだと思いますが、簡易計算であるが故に構造計算と比べて結果には振れ幅が生まれると思われ、一概にどっちの方が強いと断定はできない(ケースバイケース)と思います。
構造計算の方が結果の信頼性が高いと言えることは確かです。
私も現在建築中ですが、今後予想外の地震が来るかも知れないという事も踏まえ、許容応力度の耐震3+制振にしています。
A
回答日時:
2025/3/8 17:28:24
A
回答日時:
2025/3/8 13:21:19
制震ダンパーよりも、許容応力度計算までいかなくてもよいから構造計算で耐震等級3とすることが第一優先でしょう。
耐力壁が1.5倍あるというだけの、なんちゃって耐震等級3ではなく、きちんと「何らかの評価証明書」を取得できる、本当の耐震等級3かどうか確認しましょう。
その上で、得られるであろう「何らかの評価証明書」を元に、地震保険料の割引を受けましょう。
耐力壁が1.5倍あるというだけの、なんちゃって耐震等級3ではなく、きちんと「何らかの評価証明書」を取得できる、本当の耐震等級3かどうか確認しましょう。
その上で、得られるであろう「何らかの評価証明書」を元に、地震保険料の割引を受けましょう。
A
回答日時:
2025/3/8 13:03:37
①、建物が木造二階建て以下の住宅であれば、その制震ダンパ-の
金物とか制振装置があります。その場合は建築基準法が定めた在来
構造基準によらない、同法第37条の建築材料の品質認定があるとか、
同第68条の10の関係機関から型式認定があり、その構造計算を踏ま
えて法律基準で一体の安全率がないと、法律の1.00倍以上や1.25倍
以上も1.50倍以上でも大地震で建物の捻じれ破壊が心配です。
次、その証明とする構造基準と計算書を解らないながらも設計者から
説明を求めて、その保証も契約書へ特記の記載を求めることです。
住宅性能等級証明書を民間の建築確認審査機関のなしは同等と云います。
金物とか制振装置があります。その場合は建築基準法が定めた在来
構造基準によらない、同法第37条の建築材料の品質認定があるとか、
同第68条の10の関係機関から型式認定があり、その構造計算を踏ま
えて法律基準で一体の安全率がないと、法律の1.00倍以上や1.25倍
以上も1.50倍以上でも大地震で建物の捻じれ破壊が心配です。
次、その証明とする構造基準と計算書を解らないながらも設計者から
説明を求めて、その保証も契約書へ特記の記載を求めることです。
住宅性能等級証明書を民間の建築確認審査機関のなしは同等と云います。
8 件中、1~8件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション

3LDK以上のマンション
-
賃貸物件

ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション

駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て

南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て

リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地

南側に道路がある土地