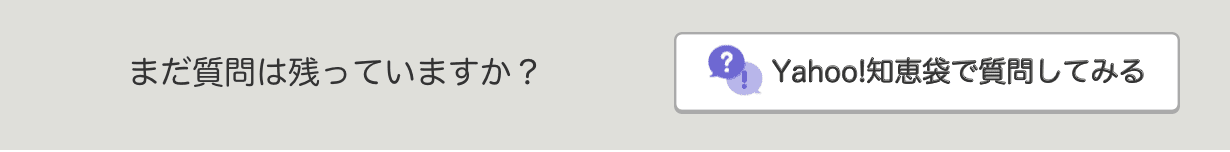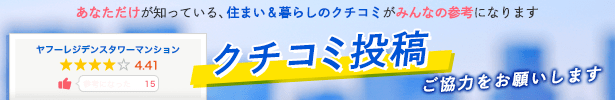教えて!住まいの先生
Q 私道に面した土地について。
私道に面した土地の購入を考えてます。
8軒ほどが共有している私道のようですが、
不動産屋からは、水道管の工事に共同で費用がかかるぐらいで、
それ以外は気にしなくて大丈夫でしょうと言われています。
私道のトラブルなど、何か気をつけるところはありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
8軒ほどが共有している私道のようですが、
不動産屋からは、水道管の工事に共同で費用がかかるぐらいで、
それ以外は気にしなくて大丈夫でしょうと言われています。
私道のトラブルなど、何か気をつけるところはありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2016/6/19 10:34:08
解決済み
解決日時:
2016/6/22 18:08:32
回答数: 5 | 閲覧数: 1029 | お礼: 0枚
共感した: 1 この質問が不快なら
回答数: 5 | 閲覧数: 1029 | お礼: 0枚
共感した: 1 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2016/6/22 18:08:32
一面でも公道に接していないと私はイヤですね。ライフラインの引き込みや道路の維持管理など出費も多くなります。
土地の評価額も低いですから、購入時はお得に思いますが行政はノータッチです
水道管も何時埋設された管ですか?
公道ならガス・水道・下水道など管理して貰えます。
知恵袋にも私道の問題は何時も挙げられているのが現状です。慎重にご検討して下さい。
土地の評価額も低いですから、購入時はお得に思いますが行政はノータッチです
水道管も何時埋設された管ですか?
公道ならガス・水道・下水道など管理して貰えます。
知恵袋にも私道の問題は何時も挙げられているのが現状です。慎重にご検討して下さい。
質問した人からのコメント
回答日時: 2016/6/22 18:08:32
皆様、ご回答ありがとうございます。
私道を甘く考え過ぎていました。
慎重に検討します。
最初に回答をくださった方をBAに選ばせていただきました。
回答
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ

私道で気を付けておくべきトラブルは、主に「通行妨害」と「掘削妨害」です。「通行妨害」は車両や人の通行を、「掘削妨害」は埋設管の修繕や工事のための掘削を、私道所有者に妨害されるトラブルです。
私道においては、所有者同士のトラブルが発生するケースが全くないとは言い切れませんので、私道所有者は誰なのか、過去にトラブルが無かったなどについて、念のため売主や仲介担当に確認されることをおススメします。
また、前述のトラブルを防ぐために私道所有者と取り交わす「無償通行および無償掘削に関する承諾書」があることが望ましいです。
まずは、上記承諾書の有無を確認された方がよろしいでしょう。
私道においては、所有者同士のトラブルが発生するケースが全くないとは言い切れませんので、私道所有者は誰なのか、過去にトラブルが無かったなどについて、念のため売主や仲介担当に確認されることをおススメします。
また、前述のトラブルを防ぐために私道所有者と取り交わす「無償通行および無償掘削に関する承諾書」があることが望ましいです。
まずは、上記承諾書の有無を確認された方がよろしいでしょう。
A
回答日時:
2016/6/19 13:59:30
8件が共有している様な場合。
例えばあなたがそこを買って、更に売ったとします。その時その土地と私道の共有持分を同時に売らないといけないのですが、たまに自分の土地だけ売って共有持分を売り忘れる人が出てくることがあります。
水道管の工事等で共有者の許可がいるのですが、このような場合にその旧所有者が共有者に含まれる場合、その人をあなたが探し出す必要があります。探せればいいですが既に死んでいたり海外に移住していたりするとかなり面倒です。
このようなリスクはありますが、その分安くなっているでしょうし、トラブルが起きない人の方が多いのも事実です。
例えばあなたがそこを買って、更に売ったとします。その時その土地と私道の共有持分を同時に売らないといけないのですが、たまに自分の土地だけ売って共有持分を売り忘れる人が出てくることがあります。
水道管の工事等で共有者の許可がいるのですが、このような場合にその旧所有者が共有者に含まれる場合、その人をあなたが探し出す必要があります。探せればいいですが既に死んでいたり海外に移住していたりするとかなり面倒です。
このようなリスクはありますが、その分安くなっているでしょうし、トラブルが起きない人の方が多いのも事実です。
A
回答日時:
2016/6/19 10:54:34
私道のトラブルなど、何か気をつけるところですね。
所有する土地と隣地との間の境界を
確定するための方法としては、まず、
境界確定訴訟を提起して、裁判上、境界を確定すると
いう方法が考えられます。
また、現在では、不動産登記法で定められている
行政制度である、筆界特定制度を利用し、
専門家の関与の下、筆界を特定することも可能です。
裁判になった場合!(トラブル想定)。
境界確定訴訟の手続の特徴
境界確定訴訟は民事訴訟の一種であり、
隣地所有者を被告として、裁判所に対して境界を確定する
ことを求めて提訴することになります。
境界確定訴訟は、「形式的形成訴訟」といわれる
特殊な訴訟類型であり、通常の訴訟と異なり、
裁判所が当事者の主張の内容や範囲に拘束されない、
境界線については当事者の自白は成立せず、
また、被告による請求の認諾も認められない、
(裁判所が原告の請求を棄却することは許されず、
一定の境界線を判決により示さなければならない、
などという特徴があります。
審理においては、当事者双方が、自己が主張する
境界線が正しい境界線であることを基礎づけるために、
過去の公図や測量図等の図面を証拠として提出し、
また、現地の検証を行うなどすることになります。
こうした証拠等に基づいて、裁判所は、原告・
被告土地の境界として、一定の境界線を確定する
内容の判決を下します。
裁判所の判決が確定した場合、
判決で示された境界線が境界として確定され、
登記簿や図面に反映することが出来ることになります
筆界特定制度
筆界特定制度は、公法上の境界である「筆界」を
特定するための行政制度です。
筆界特定制度は、土地の所有者等が、法務局に対して、
筆界の特定を求める申請を行うことにより
手続が開始されます。
手続開始後、外部専門家である筆界調査委員
(弁護士や土地家屋調査士などが選任されます)が、
法務局職員と共に、現地調査や測量等の調査を行い、
筆界に関する意見を提出し、この意見に基づいて、
筆界特定登記官が筆界を特定することになります。
筆界特定制度を利用する場合、専門家の関与の下に
筆界を特定することが実現でき
また、訴訟を提起する場合に比して迅速に
トラブルを解決することが出来るというメリットがあります。
私道トラブル
私道の通行については、通常、当事者間で明示の
合意がなされずに、土地所有者の好意等により、
事実上、私道の使用が許可されているということが多く、
そのため、権利関係が曖昧となっている場合が多々あります。
法律上認められる私道の通行権としては、以下の権利があります。
囲繞地通行権
当事者の合意の有無にかかわりなく、
民法上認められる通行権です。
通行権が認められる場合は2種類に区別されており、
まず1つ目は、自己の所有地が他の土地に囲まれており
公道に通じていない場合(袋地)には、
自己の所有地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を
通行することが認められます(有償)
また、2つ目は、1筆の土地を2筆以上に分割し、
分割によって公道に通じない土地(袋地)が
生じたときは、袋地所有者は、
他の分割者の土地(囲繞地)を通行することが認められます(無償)。
通行地役権
当事者間の合意により設定される通行権です。
私道の所有者と使用者との間で通行地役権を
設定する旨の合意をすることによって
通行地役権が成立しますが、通常、通行地役権の場合、
明示の合意がなされることは少なく、
裁判等で争われる場合、
黙示の通行地役権の設定合意の有無が問題となります。
こうした場合には、土地取得の経緯や通路の形状、
従前の通行の事実等の諸般の事情によって、
当事者間の合意の存否が判断されることになります。
所有する土地と隣地との間の境界を
確定するための方法としては、まず、
境界確定訴訟を提起して、裁判上、境界を確定すると
いう方法が考えられます。
また、現在では、不動産登記法で定められている
行政制度である、筆界特定制度を利用し、
専門家の関与の下、筆界を特定することも可能です。
裁判になった場合!(トラブル想定)。
境界確定訴訟の手続の特徴
境界確定訴訟は民事訴訟の一種であり、
隣地所有者を被告として、裁判所に対して境界を確定する
ことを求めて提訴することになります。
境界確定訴訟は、「形式的形成訴訟」といわれる
特殊な訴訟類型であり、通常の訴訟と異なり、
裁判所が当事者の主張の内容や範囲に拘束されない、
境界線については当事者の自白は成立せず、
また、被告による請求の認諾も認められない、
(裁判所が原告の請求を棄却することは許されず、
一定の境界線を判決により示さなければならない、
などという特徴があります。
審理においては、当事者双方が、自己が主張する
境界線が正しい境界線であることを基礎づけるために、
過去の公図や測量図等の図面を証拠として提出し、
また、現地の検証を行うなどすることになります。
こうした証拠等に基づいて、裁判所は、原告・
被告土地の境界として、一定の境界線を確定する
内容の判決を下します。
裁判所の判決が確定した場合、
判決で示された境界線が境界として確定され、
登記簿や図面に反映することが出来ることになります
筆界特定制度
筆界特定制度は、公法上の境界である「筆界」を
特定するための行政制度です。
筆界特定制度は、土地の所有者等が、法務局に対して、
筆界の特定を求める申請を行うことにより
手続が開始されます。
手続開始後、外部専門家である筆界調査委員
(弁護士や土地家屋調査士などが選任されます)が、
法務局職員と共に、現地調査や測量等の調査を行い、
筆界に関する意見を提出し、この意見に基づいて、
筆界特定登記官が筆界を特定することになります。
筆界特定制度を利用する場合、専門家の関与の下に
筆界を特定することが実現でき
また、訴訟を提起する場合に比して迅速に
トラブルを解決することが出来るというメリットがあります。
私道トラブル
私道の通行については、通常、当事者間で明示の
合意がなされずに、土地所有者の好意等により、
事実上、私道の使用が許可されているということが多く、
そのため、権利関係が曖昧となっている場合が多々あります。
法律上認められる私道の通行権としては、以下の権利があります。
囲繞地通行権
当事者の合意の有無にかかわりなく、
民法上認められる通行権です。
通行権が認められる場合は2種類に区別されており、
まず1つ目は、自己の所有地が他の土地に囲まれており
公道に通じていない場合(袋地)には、
自己の所有地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を
通行することが認められます(有償)
また、2つ目は、1筆の土地を2筆以上に分割し、
分割によって公道に通じない土地(袋地)が
生じたときは、袋地所有者は、
他の分割者の土地(囲繞地)を通行することが認められます(無償)。
通行地役権
当事者間の合意により設定される通行権です。
私道の所有者と使用者との間で通行地役権を
設定する旨の合意をすることによって
通行地役権が成立しますが、通常、通行地役権の場合、
明示の合意がなされることは少なく、
裁判等で争われる場合、
黙示の通行地役権の設定合意の有無が問題となります。
こうした場合には、土地取得の経緯や通路の形状、
従前の通行の事実等の諸般の事情によって、
当事者間の合意の存否が判断されることになります。
A
回答日時:
2016/6/19 10:53:21
私道は、お勧めできません。
道路の修理で、負担を拒否する輩がいますからね。
道路の入り口ならいいとして、奥の方が陥没したり
すると、手前の方は通らない事を理由に支払を
しないケースがあります。
道路工事(水道、下水工事)をするには、全員の同意を
必要としますから、ややこしいですよ。
以前、空き地に下水工事をするのに、道路を掘削工事を
するのに、同意書に中々印鑑をくれない方が
いて苦労した事があります。
購入するんであれば、水道も下水も引き込み済みの
物件にしてください。
それが、無くて後年になって、やろうとして同意が
得られず、家が建てられなかった事例もあります。
草刈もせず放置していて、回りに迷惑をかけていた
つけのようですがね。
道路の修理で、負担を拒否する輩がいますからね。
道路の入り口ならいいとして、奥の方が陥没したり
すると、手前の方は通らない事を理由に支払を
しないケースがあります。
道路工事(水道、下水工事)をするには、全員の同意を
必要としますから、ややこしいですよ。
以前、空き地に下水工事をするのに、道路を掘削工事を
するのに、同意書に中々印鑑をくれない方が
いて苦労した事があります。
購入するんであれば、水道も下水も引き込み済みの
物件にしてください。
それが、無くて後年になって、やろうとして同意が
得られず、家が建てられなかった事例もあります。
草刈もせず放置していて、回りに迷惑をかけていた
つけのようですがね。
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
土地

南側に道路がある土地
-
土地

前道6メートル以上の土地
-
土地

平坦地の土地