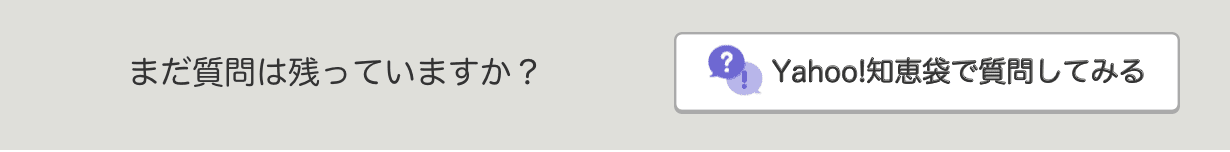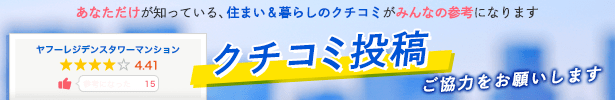教えて!住まいの先生
Q 建築詳しいかた。制震ダンパーの付いた木造軸組工法と2×4ならどちらを選びますか?
質問日時:
2023/7/16 16:57:14
解決済み
解決日時:
2023/7/21 20:21:21
回答数: 8 | 閲覧数: 264 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 8 | 閲覧数: 264 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/7/21 20:21:21
自動車部品メーカーの設計開発をしていました。建築の専門家ではないですが、木造軸組工パネル工法にプラスして制振ダンパーを昨年建てた自宅ではOPで選択できたのですが、止めました。
https://www.tokiwa-system.com/column/column-177/に簡単に解説されている内容を参考にするなら。
・コンパクトで設置がしやすく間取りに影響しない オイルダンパー
・小さな揺れから大きい揺れまで吸収する オイルダンパー・粘弾性ダンパー
・折れたり気温の影響を受けて劣化したりせず耐用年数が長い オイルダンパー
と解説されています。
基本的な構造は自動車のショックアブソーバーと同様と思われます。
となると、問題は耐久性でしょう。
オイルの粘性で地震の外部入力を、熱に変換して揺れを減衰する構造ですから、オイルの粘性が低下したら、制震性能が低下します。
よく見かける免震構造も、ゴムの劣化で交換期間が決まっています。
新築後10年や20年では性能劣化は少ないでしょうが、何十年も取り替えなしで本当に制震性能が保証されているのか疑問でしたので、木造軸組工パネル工法+軸組部の金具補強タイプにしました。
当初2×4にしたかったのですが、そのHMでは最高級グレードになってしまうので、予算上で断念しました。
私見ですが、2×4か木造軸組工パネル工法で、金具がしっかり入って居るなら、そちらを選びます。
1軒目の自宅は築26年目ですが、未だに障子のサッシが隙間無く閉まります。
車で言うモノコックは建物の変形も少ないと思いました。
本来なら免震構造が理想ですが、メンテも含めると高価なので、当方は総2階建て、大量壁の直下率を上げて、耐震性能を挙げておきました。
20年くらいで制振ダンパーを交換できるならと思うのですけどね。
https://www.tokiwa-system.com/column/column-177/に簡単に解説されている内容を参考にするなら。
・コンパクトで設置がしやすく間取りに影響しない オイルダンパー
・小さな揺れから大きい揺れまで吸収する オイルダンパー・粘弾性ダンパー
・折れたり気温の影響を受けて劣化したりせず耐用年数が長い オイルダンパー
と解説されています。
基本的な構造は自動車のショックアブソーバーと同様と思われます。
となると、問題は耐久性でしょう。
オイルの粘性で地震の外部入力を、熱に変換して揺れを減衰する構造ですから、オイルの粘性が低下したら、制震性能が低下します。
よく見かける免震構造も、ゴムの劣化で交換期間が決まっています。
新築後10年や20年では性能劣化は少ないでしょうが、何十年も取り替えなしで本当に制震性能が保証されているのか疑問でしたので、木造軸組工パネル工法+軸組部の金具補強タイプにしました。
当初2×4にしたかったのですが、そのHMでは最高級グレードになってしまうので、予算上で断念しました。
私見ですが、2×4か木造軸組工パネル工法で、金具がしっかり入って居るなら、そちらを選びます。
1軒目の自宅は築26年目ですが、未だに障子のサッシが隙間無く閉まります。
車で言うモノコックは建物の変形も少ないと思いました。
本来なら免震構造が理想ですが、メンテも含めると高価なので、当方は総2階建て、大量壁の直下率を上げて、耐震性能を挙げておきました。
20年くらいで制振ダンパーを交換できるならと思うのですけどね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/7/21 20:21:21
ありがとうございました^_^
回答
7 件中、1~7件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2023/7/17 09:53:26
この二つに一つは、建築に関しては少し強引であって、だから他の回答者さんは第3・第4の選択肢を提案していると思います。
そもそも制震ダンパーを付けたから等級が上がったと言う話はあまり聞きません。
木造軸組みのみの構造で耐震性能が判断されると思います。
確かに効果的なダンパーは有ると思いますが、価格上乗せに使われている様な感じがしてしまいました。
そんな不信感から、自分は将来的な事も考えず、2×4を選択してしまいそうです。
でもケースバイケースである事の方が圧倒的に多いと思います。
そもそも制震ダンパーを付けたから等級が上がったと言う話はあまり聞きません。
木造軸組みのみの構造で耐震性能が判断されると思います。
確かに効果的なダンパーは有ると思いますが、価格上乗せに使われている様な感じがしてしまいました。
そんな不信感から、自分は将来的な事も考えず、2×4を選択してしまいそうです。
でもケースバイケースである事の方が圧倒的に多いと思います。
A
回答日時:
2023/7/17 08:36:34
A
回答日時:
2023/7/17 01:58:14
A
回答日時:
2023/7/16 21:12:21
木造で制震ダンパーって全くいらないので、選ぶ材料にはなりません。
最低限耐震等級3が取れれば、あとは予算と間取りで好きな方で良いです。
最低限耐震等級3が取れれば、あとは予算と間取りで好きな方で良いです。
A
回答日時:
2023/7/16 20:20:53
①戸建ての「木造住宅」向けの「制振装置」で、マトモな製品は未だに見た事がありませんので、採用しない方が良いですよ。 これは「オイルダンパー方式」でも「ゴムの粘性方式」でも同じ事なので、参考にしてください。
②但し2×4工法にも色々な問題点があって、将来「リノベーション」をしたい時に、様々な規制から思う様な工事が出来ない可能性もありますので、その点はご理解ください。
https://w-wallet.com/woodframeconstruction6.html
③費用の面を考えないのであれば、この様な木造もありますので、参考にしてください。
1.木質ラーメン工法:
住友林業では「ビックフレーム工法」と言う名前で販売していますが、どこの建築会社でも扱う事が出来るのが、この工法の特徴です。
https://shelter.inc/purpose/5740
この様な巨大な庁舎も作れるので、参考にしてください。
2.CLT工法:
「クロス・ラミネーテッド・ティンバー」と言います。 欧米ではこの様な巨大な木造の建物が建てられていますし、日本でも40階建ての木造ビルが検討されていますので、参考にしてください。
https://shelter.inc/purpose/5740
④この様に「木造」には多種多様な工法が存在するのですが、「戸建て住宅」に限って言えば、「費用対効果(コストパフォーマンス)」と「耐震性能」が一番高いのは、「在来工法」で「耐震等級3」にする事なので、覚えておいてくださいね。
②但し2×4工法にも色々な問題点があって、将来「リノベーション」をしたい時に、様々な規制から思う様な工事が出来ない可能性もありますので、その点はご理解ください。
https://w-wallet.com/woodframeconstruction6.html
③費用の面を考えないのであれば、この様な木造もありますので、参考にしてください。
1.木質ラーメン工法:
住友林業では「ビックフレーム工法」と言う名前で販売していますが、どこの建築会社でも扱う事が出来るのが、この工法の特徴です。
https://shelter.inc/purpose/5740
この様な巨大な庁舎も作れるので、参考にしてください。
2.CLT工法:
「クロス・ラミネーテッド・ティンバー」と言います。 欧米ではこの様な巨大な木造の建物が建てられていますし、日本でも40階建ての木造ビルが検討されていますので、参考にしてください。
https://shelter.inc/purpose/5740
④この様に「木造」には多種多様な工法が存在するのですが、「戸建て住宅」に限って言えば、「費用対効果(コストパフォーマンス)」と「耐震性能」が一番高いのは、「在来工法」で「耐震等級3」にする事なので、覚えておいてくださいね。
A
回答日時:
2023/7/16 17:13:09
制震ダンパー否定派。
耐震等級3を選びます。
耐震等級3を選びます。
A
回答日時:
2023/7/16 17:11:54
☆、木造軸組みや木造枠組み構造でも制震ダンパ-金物は、その金物は、
地震の揺れを制御も耐震壁と釣合いよく、一体性のある動きを構造計算
でされないと、逆に地震で建物の捻じれ損壊の原因となると思います。
地震の揺れを制御も耐震壁と釣合いよく、一体性のある動きを構造計算
でされないと、逆に地震で建物の捻じれ損壊の原因となると思います。
7 件中、1~7件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築戸建て

4000万円以内の新築一戸建て
-
新築戸建て

駅まで徒歩10分以内の新築一戸建て
-
新築戸建て

南側に道路がある新築一戸建て
-
新築戸建て

総区画数50戸以上の大規模分譲地の新築一戸建て
-
新築戸建て

駐車場が2台以上ある一戸建て
-
新築戸建て

間取り変更可能な新築一戸建て